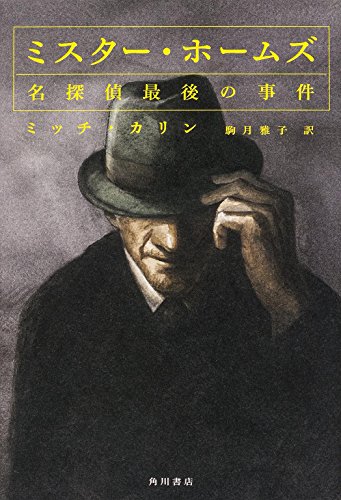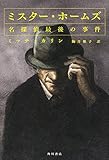書いた人:横倉浩一 2016年4月書評王
都内の私立男子校で国語を教えてます。大学院時代の専門は近世文学。上田秋成や井原西鶴を主に読んでいました。サッカー部・演劇部泡沫顧問。図書館部長。スポーツではNBAとツールドフランス、ボクシングなどを好んで観戦。毎年、徳之島に闘牛を見に行くことを恒例としています。飲みには行くがお酒は飲めない。バツイチ独身。
『ミスター・ホームズ』は言うまでもなくシャーロックホームズパスティーシュ作品の一つだ。ただし本作の主人公は、大ヒットしたカンバーバッチ版ホームズのようなスタイリッシュで都会的な華麗さとは対極にある。いつも不安や後悔の念にさいなまれ、迷ったりぼんやりしたりめそめそしたりと、およそ華麗とはほど遠い。それでもカリン・ホームズが老舗ファン団体〈ベイカー・ストリート・イレギュラーズ〉会長はじめ、多くのシャーロック愛好家たちに受け入れられたのは、その秀逸な構成と設定のゆえだろう。ここでのホームズは、事件簿を書いた相棒ワトソンや挿絵画家のねつ造によって巷間に流布している《虚像》、いわゆる快刀乱麻のヒーロー像や「パイプに鳥打ち帽」の名探偵像にむしろ「やれやれ」と辟易している老境の男として登場する。その言動には愛好家たちをして「《本物》のホームズってこんな感じだったかも?」なんて思わしめるリアリティがある。むろん「ホームズなんて、もともと実在しないから!」なんてツッコミは無しだ。
この物語には三つの世界が存在し、時に連想の糸で繋がりながら同時進行する。
一つはこの小説の基調をなす1947年のパート。とうに探偵業を引退した93歳のホームズがサセックス州の田舎で養蜂業を営んでいる。家政婦マンロー夫人とその子ロジャーとの三人暮らし。ホームズは利発なロジャーを自分の孫のように愛している。該博な知識と観察力で多くの難局を乗り切ってきた知性も翳りを見せ、そのことに怯えるホームズは老化防止に効果ありとされるローヤルゼリーに執着する。
二つ目はロジャー達との日常の中で回想される、戻ってきたばかりの日本への旅のパート。これまた老化防止効果が望める植物・サンショウについて意見交換し親交を深めてきたウメザキの招待を受け、敗戦の傷跡も生々しい日本をはるばる訪れた。ウメザキの住む神戸からサンショウの自生する下関までの旅の過程で、ホームズは次第にウメザキが自分を日本に招いた真の目的に気付いていく。それはウメザキの父の喪失にまつわる、悲劇的な因縁ともいえるものであった。
第三のパートはホームズが語り手となって1902年の事件を自ら書き記した体裁をとる『グラス・アルモニカの事件』。二人の子を続けて流産し、悲しみにくれる若妻アン。その心を癒すため、夫のケラーはグラス・アルモニカなる楽器の演奏を彼女に勧める。しかしそのアルモニカ熱は次第に歯止めの利かぬものとなり、やがては演奏を通して死んだ子供と感応し、霊的交流にふけるところまで昂じてしまう。見かねた夫は強引に妻から楽器演奏の機会を取り上げる。だがその後も妻は音楽家のもとに密かに通っているのではないかと疑ったケラーは、アンの調査を依頼すべくホームズのもとを訪れた。当初それは何の変哲もない〈平凡な案件〉と思われた。しかし予想に反してホームズの人生はこのアンとの出会いを機に大きく歪められることとなる。まさにアンはホームズにとってのファムファタル=運命の女であった。
喪失の痛みがそこには描かれている。前半おもに描かれるのは《自分》を失う痛み。〈それはただの滑稽な話では済まされない、ぞっとするほど恐ろしいことなのだ〉。ずっと自分を支えてきた知性、その基盤をなす記憶力を失う不安・恐怖はいかばかりのものか。《あの》ホームズだからこそ真底〈ぞっとする〉のだ。そして物語が後半に進むにしたがって浮上してくるのは《誰か》を失う痛みだ。ロジャーが父を、アンが未生の子を、ウメザキが父を失った悲しみ・痛みが真に迫ってホームズに、あるいは私たち読者に実感されるまで、物語の後半を待たねばならない。失うとはこんなにも痛いことなのだ、そして失ってなお生き続ける意味を見いだすことは、〈平凡〉でも何でも無く、こんなにも困難なことなのだと、ミッチ・カリンの容赦ない物語が私たちに思い知らせてくれるはずだ。