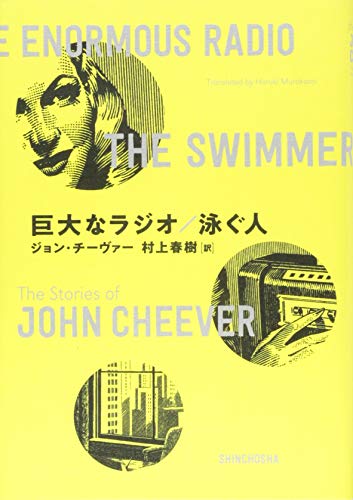日記文学、というジャンルがある。平安版・夢見るオタク少女の回想記である『更級日記』、何気ない出来事を独特の観察眼で綴った武田百合子の『富士日記』など、日々の記録から生活を覗き見しつつ追体験できるような親近感と、そこから浮かびあがる社会の空気感を味わえるのが魅力の日記文学界に、平成生まれの新星が現れた。その名を少年アヤという。
学生時代からWEB上で綴っていた日記が評判となり、2014年『尼のような子』を出版。<好きな男の子が、ドライブへ連れていってくれました>ではじまる本書には、その男の子にふられるまでの顛末、失恋の傷を埋めるように韓流アイドルに依存してグッズを買い漁る日々、露出狂との遭遇や肛門を患っての病院通い、という欲望のままに迷走する様子が自虐と笑いのオブラートで包んだ言葉で描かれている。
この頃のアヤちゃんは「おかま」を自称していて、そのラベルを自ら貼り付けることで世の中と折り合いをつけ、コンプレックスを喜劇に昇華するべく日記を綴るようなスタイルだった。ところが二作目の『少年アヤちゃん焦心日記』では、客観的な視点で自分をネタにする手法はそのままに、「男らしさ」を期待されて傷ついてきた幼少期や、揺らぐセクシュアリティについての葛藤など、自己の内面を真摯に見つめる描写が目立つ。満員電車で痴漢にあったこと、高校時代に付き合っていた彼女のこと。そして自分の中の<おとこのこの解放>と称してその彼女と再会した後の行動には、正直はらはらがとまらない。どこに向かっているのだろう、アヤちゃんは。しかし、この心のうつろいこそが日常を活写するリアルであり、日記文学の醍醐味ではないだろうか。一日一日をつぶさに観察した記録としての生身の言葉。それは小説とは違う強さで胸を打つのだ。
そして彼は「おかま」の自称をやめる。ラベルを剥がしてまっさらになった心境の変化が、三作目『果てしのない世界め』に表れている。<ぼくは、ずっと自分の性別がわからなかった>と告白し、<ピストルやミニカーを欲しがるような、ふつうの男の子>じゃなかった自分と家族との関係を、私小説風に描いているのだ。ドレスを着たお姫さまの人形を買ってくれた祖父と、それを罪人のような顔で見つめる母親。過去の記憶や傷をこまかく掬いあげ、物語として再生するような詩情あふれる文章も素晴らしいけれど、ドライブ感とキレのある日記はもう読めないのかな、と少々寂しく思ってもいた。
しかし嬉しいことに最新刊『なまものを生きる』は、原点回帰となる日記エッセイだ。なんとアヤちゃんは<びんぼうになっちゃった>そうである。実家を出て一人で暮らしているのにバイトもせず、ヤフオクで昔から集めていたおもちゃを売って生活しているのだから、そりゃそうだ。でもそれでいい、と彼はいう。おかまという着ぐるみで自分をごまかして社会と関わっていた頃よりも、<弱々しくても、臆病でも、ただの自分である方がずっといい>のだ、と。どんなデコボコな道を歩んでアヤちゃんがそう信じられるようになったかを、これまで著作を読んできた人は切ないほど知っている。だからこそ、応援せずにはいられなくなってしまう。あいかわらず、すぐお腹を壊したり歯医者トラブルに巻き込まれたりしているけれど、以前よりほんの少し風通しよく、同じくびんぼうな友人たちに支えられながら日常を楽しんでいる様子がたのもしい。
そう、この本は巻末の謝辞に記されているように<友人たちへ>と向けられたものだ。男や女である前にその人なのだ、ということを思い出させてくれる現実の友人たちへ。性別によって価値観が制限されることなく、誰が何を愛そうとそれでいいのだと知っているすべての人々へ。そしてこれからこの本を読むであろう人が、男の子だからってキラキラした可愛いものを好きだと言えないような不自由な時代があったなんて!とおどろく日が、そう遠くない未来にくるはずだ。彼の繊細すぎる魂から紡ぎ出された言葉には、そんな風に願いたくなる力が秘められている。
2019年8月書評王:小林紗千子
少年アヤちゃんといえば、昔イベントでサインをもらう時に名前を告げたところ「マジで〜!」と大笑いしていたことを思い出します。かわいかった。
【紹介した本】