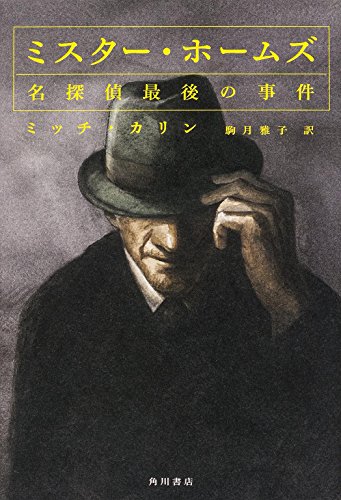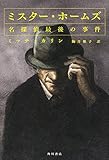書いた人:瀧源舞(たきもとまい) 2016年7月書評王
普通の会社員。小さい頃に従姉から借りたままの小説をまだ持っているほど、本は大事に扱うようにしている。パクチーはシャンツァイもしくはコリアンダーと呼びたい。
night、Nacht、gece、notte、noche、aften、nox、nuit、そして夜。
“夜”を表わす単語は国によってそれぞれで、どれもが似てはいるけれど違う響きを持っている。想起されるイメージは、個人の体験や記憶によって異なるだろう。けれど、本書に書かれている“夜”は、時代や土地を問わず、だれもが「あぁ、これは知っている」と錯覚するのではないか。自分の中には存在しないかもしれない夜を、物語の中に見てしまう。それは、夏の夜という舞台装置が持つ作用によるものなのか、それともミルハウザー流の魔法なのか。
時刻は真夜中すぎ。いまだ眠りにつこうとしない者がいる。何かに突き動かされるように部屋を飛び出す14歳のローラ。窓辺で膝をつき約束した誰かを待つジャネット。あまり見込みのない小説を一人きりで書き続けるハヴァストロー。桃色のドレスをまとってショーウィンドウの中で憂鬱を持て余すマネキンと彼女に恋する車体工場士のクープ。月明かりが差し込む屋根裏部屋で動き出すほこりをかぶった人形たち。音もなく家に押し入り、冷蔵庫マグネットや眼鏡ケースなどささいなものを盗んでは「私たちはあなた方の娘です」という置手紙を残していく女子高生の窃盗団。彼らの身に起こるエピソードが少しだけ重なり合いながら、夜は更けていく。
舞台は米コネチカットらしいが、町の全体像はよくわからない。ミルハウザーの描く場所は、地名が書かれていても、いつも、どこにもない場所のように感じられる。線路の上に立つ黒い鉄の跨線信号台、メインストリートにある百貨店。色づく前のサトウカエデの木々。恋人たちと独り者しかいなくなった浜辺。彼らと一緒にそこここを歩くうちに、それほど大きくはない町を発見していく。
時折、そんな彼らを眺めているような存在を感じる。月光の描写が繰り返し出てくることから、正体は月かと思ったが、そうでもなさそうだ。なぜなら中盤以降、月の女神もまた庭で眠り込む少年の横顔に魅せられ、地上に降りてきてしまうからだ。では、小説の創造主である作者・ミルハウザーの視点かというとそうでもない。三人称がもたらす効果だけではなく、登場人物を見ている別の視点があるように思えるのだが、どうもはっきりしない。
時間の流れ方も不思議だ。作中の出来事は現在進行形で語られているはずなのに、登場人物の何人かは、かつてあった一瞬を思いだしているような感覚に捉われ、記憶が揺れる。まるで今夜のこの瞬間だけが、連続する時間からはぐれてしまったかのようだ。肌に触れるあたたかい夜風まで感じ取れるような描写とともに、そうした感覚のゆらぎが、それとは気づかない程度に挿入されている。
これまでのところ、ミルハウザー作品のほとんどは、彼に惚れ込んだ柴田元幸によって翻訳されている。英米文学に関する広い知識と深い洞察はもちろん、作家への親愛の情がにじむ訳者解説は、作品世界への最適な導き手だ。初期に書かれた短編集『イン・ザ・ペニー・アーケード』の解説によると、ミルハウザーの描く人物は、誰もが退屈しているという。<現実に対する、自分がいまここにあることに対する異議申し立てとしての退屈〉を抱えているという。たしかに本書に出てくる人々もまた、くまなく全身を退屈に覆われながら、夜が与えてくれる変化に焦がれている。
ミルハウザーが描く人物には、芸術家や職人、子供が多い。そしてしばしば、自分を魅了するものを追い求めるうちに、あちら側の世界へ行きかける。たいていの場合、それが大人であればあちらへ行ったままで、子供であればこちらに戻ってくる。その意味では本書に出てくる者たちは、年齢に関係なく子供に近いのかもしれない。あともう少しで、夜はその座を朝に明け渡すだろうから。
しかし夜は明けても話は“おしまい”にはならない。どういうわけか、ミルハウザーの書く物語は、その後に起こるであろう変容の方が気にかかってしまうのである。