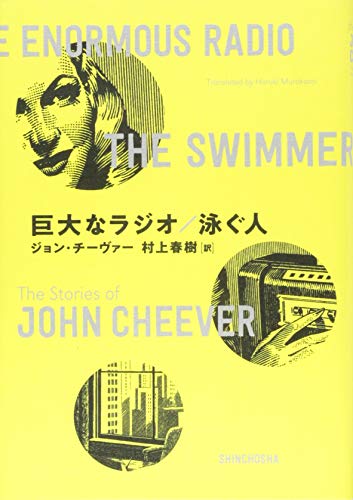書いた人:関根弥生 2019年2月社長賞
2018年11月から書評講座を受講しています。→Pia-no-jaC←ファン。公務員。
村田喜代子は老女を描くのがうまい。『蟹女』や『望潮』などうっすらと漂う狂気に戦慄させられる作品も多いが、『エリザベスの友達』は少し趣が異なる。本作では、介護付き有料老人ホーム〈ひかりの里〉を終の棲家と定めた老男老女たちの、夢と現が入り混じる日常と、時代に翻弄されながら歩んできた半生が語られるが、皺の奥に隠された少女のかわいらしさや、記憶というものの豊かさと不思議が強く印象に残る。
110号室の初音さんは97歳。認知症が進み、日がな一日〈うつらうつら過ごしている〉。見舞いに通う二人の娘のことも、もう誰とわからないでいる。初音さんは夕方になると、〈それではお暇いたします〉とどこかに帰っていこうとするが、その魂の行き先は、二十歳で結婚したハンサムな夫と共に渡った天津だ。
この地で生まれ、6歳まで過ごした長女満州美が〈蜃気楼だった〉と述懐する天津は、日仏英等各国の租界が置かれ、戦乱の最中にあってもここだけは美しい緑の中での競馬観戦や、サーカスの猛獣ショーに興じる贅沢が守られた別天地であったという。初音さんも、駐在員の奥様達と互いを〈エヴァ〉や〈サラ〉とイングリッシュ・ネームで呼び合い、昼下がりのお茶や買い物を楽しむ華やかな時を過ごした。また、天津は日本の女性にとって〈夫から、おまえとは呼ばれなかった〉〈嫌なら、ノー!と言うことができた〉本当の自由を手にした場所でもあったのだ。
認知症によって〈時空をすり抜けて行く〉のは、初音さんだけではない。隣室の牛枝さんは、男の子ばかり三人続いた後に生まれ、戦争に駆り出されることのない牛にあやかろうと名付けられた。牛枝さんが夢で逢うのは、戦死した初恋の相手や、兄弟同然に育った三頭の馬たちだ。馬たちは揃って大きな眸(め)を向けて〈はよ、こっちきまっしょ〉と冥府へ誘う。
〈認知症は自由です〉と若い介護士は言う。記憶という積み木の積み方を変えることで、〈別の人生やら過去やらがいろいろ出来る〉のだから。天津時代〈サラ〉と呼ばれた初音さんは、前任の所長夫人で、異国での暮らしを導いてくれた〈エヴァ〉鞠子さんの記憶も取り込み、初音さん自身は出会う機会が訪れなかったはずの、清朝最後の皇帝溥儀の妻で〈エリザベス〉と呼ばれた婉容とも夢の中で邂逅を果たす。記憶を積み直すことで、自己と他者、此岸と彼岸を隔てていたものが融けだし、その境界はどんどん朧になってゆく。
記憶の積み木を手にするきっかけは、ジャスミンティの香りや、古い写真だったりするが、中でも〈音楽の喚起力はなんと強いものか〉と満州美は感嘆する。ボランティアの歌う韓国民謡や軍歌が、何十年もの時間を一気に巻き戻し、〈人間の抜け殻〉のようだった年寄りたちが束の間集い、嗄れた喉を振り絞って唱和する。しかし、立ち戻ったその時が、深い後悔と慚愧の念に満ちている者もある。『満州娘』を耳にした途端、慟哭し誰かに許しを求め続ける元満州関東軍兵士の姿。いったいどれほどのことがあったのか。その答えを知るものは誰もいない。
牛枝さんの娘が言うように、認知症によって人の記憶や魂が、雲母のようにサラサラと剥がれ落ちていくものなのだとしたら、最期まで人の魂の核として残るものはいったい何だろう。それが自責や悔恨の念だけでないことを願うばかりだ。
天津が大戦の挟間に浮かんだ蜃気楼だったとしたら、〈ひかりの里〉もまた、生と死の合間に現れる蜃気楼なのではないか。小さな貝のような部屋から吐きだされた記憶や想いが扉の隙間から漂い出して混ざり合い、ほのかな明るさを宿してホーム全体を包み込んでいるように見えるのだ。誰も避けることができない〝そのとき″の迎え方を考えると、ピンピンコロリだけではない、こんな終焉もありだと思える。